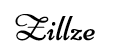共存思想だった子供の副人格をレイキで癒していく。

 Kindle版
Kindle版
さよなら、ツインレイ
当時はこれでおしまいなんだ・・・。そんな風に思いながら書いた『さよならツインレイ』。結果的にさよならしたのは、神交法の相手であるツインレイの霊体だった件。今更振り返って読んでみると納得がいく一冊だが、当時はよくわかっていなかった。
kindleの読み放題『Kindle Unlimited30日間の無料体験』では、ほかの三冊も同時に読み放題
人の相談にのり、メールを送ったあと、なぜか私のなかに怒りが込み上げてきた。
私は怒っているのである。
レイキを当て乍ら「怒っている子」を探してみたところ、小さな子供の私が出てきた。
「なんで、なとちゃ以外の誰かをかまうの!」とプンプンと怒っている。
自分が一番じゃないと気が済まない私がいた。
どうやら、子供のなとちゃは『人と関わっている私』に怒っているようで、ハタからみれば、私が私に怒っているような状態となっている。
子供のなとちゃにとって、私はママなのだ。
「ごめんね、なとちゃが一番に大事だよ。」と伝えると、涙が流れた。
本当に? 本当に?
そんな風に聞いてくるが、心のなかでは罪悪感でいっぱいになった。
なとちゃは誰かの一番になってしまうと、誰かほかの人が二番になってしまう。それが罪悪感となっている。
本当はわかってる、でも、どうしても自分がママの一番になりたいっていう気持ちが葛藤を起こしていた。
そして、なとちゃは一番を誰かに譲り、自分をどんどんと下げていくことになった。
自分はあとでいい。
なとちゃはひとしきり泣いて、自分が一番でもいいことを理解した。
私は私の一番であり続けている。もし、誰かを優先していても、心のなかではずっと私が一番である。
罪悪感はどこからやってくるのか。それは自分が一番になってはいけないっていう心理にあった。
それでもまだ癒しきれていないようで、どうして『一番になりたいのか』を教えてくれた。
さびしい。
子供のなとちゃはそう言って泣いた。
さびしい。さびしいから自分を優先してほしかった。特に一番になりたかったわけじゃない、さびしいから自分を優先にしてほしかったんだけれど、優先してもらったら誰かが困ってしまう。だから、自分を優先しなくなった。
なとちゃのなかで「さびしさは優先順位が低くなった」ときだった。
なとちゃのなかにあるさびしい感情は受け取られなくなった。誰かにさびしいと寄り添うこともなくなり、ただただ寂しい感情を実感するような子になった。
そのさびしさを癒し始め「いっしょにいるよ」って話をしていたところ、「共存」というワードが飛び出てきた。
子供のなとちゃの世界は狭かった。
ママとなとちゃ、そしてそれ以外の人たち。
なとちゃはそれ以外の人たちと共存することが出来なかった。
「共存していく」ってことに、なとちゃは強い拒絶反応を示したけれど、さびしいを受け入れてもらえ、優先されてもいいことも受け入れられたなとちゃは『共存』を受け入れていった。
『敬語』というワードがでてきた。
私は敬語が苦手だった。ふとしたときにタメグチになってしまうぐらいには敬語が苦手で、敬語で話すことがことさら苦手なものだから、上司にもよく叱られたものである。
途中で「社会適応がないんだろうな」ってことで、敬語で話すことへの執着も無くなり、たいていはタメグチで過ごしている。
共存とは序列とは関係がないはずなんだが、私は敬語をかなり幼少期から教えられたようである。
それゆえに「目上の存在には敬語を使いましょう」ってことになるんだが、このときに私の世界は崩壊した。
この世界は共存ではなかった。元々私の世界は共存にあったんだが、私の世界は序列の世界となった。
敬語というものを教えられたときに、優劣があることを知ってしまい、自分が『優先』か『あとか』という意識が生じたようである。
実は私の優劣意識は『敬語』という概念から生じたもので、それ以前はずっと『優劣はない』世界にいた。
私は小さい時『みんな対等、共存』という世界に生きてきた。
だけれど、敬語を教えられて『みんな対等ではない』ことを理解したとき、私は『優劣が存在している』ことも理解したようである。
すべてが壊れてしまったのは「敬語を使いましょう」ってことだった。
私はツインレイの彼に「なとちゃはどうして一番最後なの!」と怒ったりもしていた。そして自分を優先してもらえたとき、罪悪感で怯えていた。
私の子供人格は、ツインレイの彼にしっかりと自分をアピールしていた。